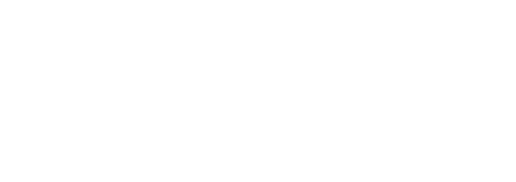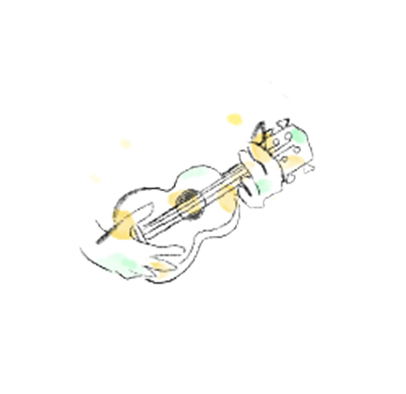2025.06.24
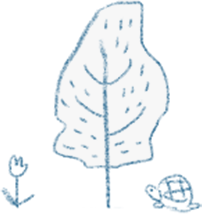
 6/24:家事と武道
6/24:家事と武道
わたしたちが提供している「生活援助」において、お客様に喜んでもらえる人とそうでない人の、その違いについてなるほど~と思う文章にふれましたので引用してみたいとおもいます。
「家事というのは、本質的に他人の身体を配慮する技術なのだと思う。
清潔な部屋の、乾いた布団に寝かせ、着心地のよい服を着せて、栄養のある美味しい食事を食べさせる。どれも他者の身体が経験する生理的な快適さを想像的に先取りする能力を必要とする。家事においては、具体的な技術以上に、その想像力がたいせつなのだと思う。」
「~家事に必要なのは、他者からの「呼びかけ」に即応する同期する力だと私は思っている。
もちろん日々の穏やかな生活において、私たちが「家事能力」と呼ぶのは、共に暮らす人たちからの「快適な住環境」や「美味しい食事」や「きちんとした衣服」を求める穏やかな「呼びかけ」を聴き取ることができる能力を前提にしている。どれほど「きれい好き」でも、疲れて眠っている家族の頭で朝から掃除機をぶん回したりする人のことは「家事能力がある」とは言わない。どれほど「料理がうまく」ても、食べすぎで体調が悪い家族の前に高カロリーのディッシュを並べる人のことは「家事能力がある」とは言わない。いくら「きちんとした衣類好き」であっても、家族が気に入っているボロボロのジーンズやよれよれのポロシャツを「見苦しい」とゴミに出してしまう人のことは「家事能力がある」とは言わない。家事能力というのは、具体的な家事処理能力のことではなく、突き詰めて言えば、共に生活している人の愁訴を聴き取る力のことである。寒いとか、疲れたとか、腹減ったとか、眠いとか、誰かに抱きしめて欲しいとか……そういう無言の訴えを感知する力のことである。そういうふうに定義する人はあまりいないと思うが、私はそう思う。」
内田樹氏の「武道論:「家事と武道」P111、P121」からそのまま引用しました。
わたしもそう思います。
いつごろからか、私は母の料理にどこか心に抵抗がありました。どうしてそう感じるのかうまくは言えなかったのですが、いまはわたし自身が家事をするようになり、その違いを自分自身で感じています。
私自身は家事を「ぬくもり」を届ける、合いある行為だと思っています。お風呂に入って、気持ちのいい衣類を身にまとい、食事はまさにそのものを通じて体に熱量を届けます。家事をしてもらう人自身に「わたしのことはわかってくれている」という気持ちがうまれていなければ、ただの「作業」なのかなと思います。
家事はわたしたちの仕事の大きな部分を占めています。その仕事について、私たち自身がきちんと定義しておくことは大きな責任だと私は考えます。